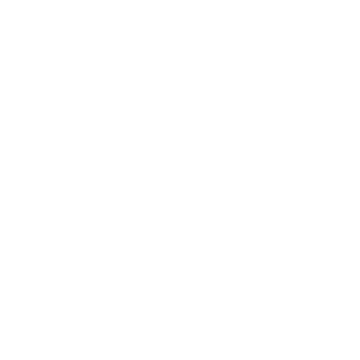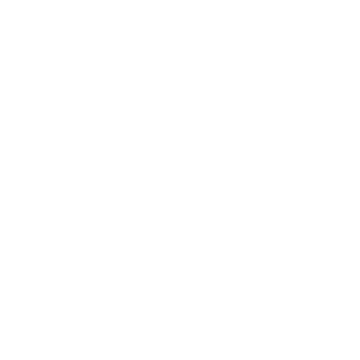斬魔の勇士 メイコ

戦いが終われば、花が芽吹く。メイコはその花だった。血という水を与えられ、非道な世界で育ちながらも、彼女が同じ過ちを繰り返すことはなかった。民を守るため、驕ることなくその身を捧げる剣聖であったメイコは、無情なる世界において得難き美を楽しむことを忘れぬ数少ない戦士として、愛されていた。その心持ちゆえか、彼女は戦いの最中でも笑みを湛えている。その瞳の輝きは、いかなる状況でも失われることはなかった。しかし、妖魔たちが牢獄から解き放たれたとき、メイコの心に試練が訪れた。
悪鬼たちが、数百年の長き眠りから覚め、御沼に解き放たれた。弟のモトオリが連れ去られたとき、メイコの中で何かが変わった。その美貌に影が差し、微笑みは消えた。彼女は妖魔を打ち倒すため、「魔物の短剣」を手に取ることを心に決める。この短剣は、妖魔を打ち倒すことのできる唯一の武器だという。しかし、それを振るう者には、大きな代償が課せられるのだった。斬り倒した妖魔はすべて、その短剣の内に取り込まれた。倒せば倒すほど、より強力な剣となっていき、それを振るう者をより強く蝕むようになっていった。しかし、メイコに選択の余地はなかった。弟を救える可能性が少しでもあるなら、自身の「内と外」より襲い掛かる妖魔に立ち向かうほかなかった。
苦悩の亡霊

パート1
メイコの背後で、モトオリが濡れた地面を歩く音がする。そのとき、メイコは弟の方を振り返り、彼はもう一人前なのだからと思い直した。目の前にある重い木の扉を見つめることしかできないメイコだったが、全力で走っているというのに、その扉はあまりに遠く感じられた。彼女はずっと、弟の面倒をみてきた。幼い頃に両親を亡くした彼女は、弟を育てることを自らの使命としてきた。弟の世話をし、弟のために商売をし、弟が常に屋根の下で暮らせるようにした。ある日、幼いモトオリがあざだらけになるまで殴られ、その頬に乾いた涙の跡を残したまま帰ってきたことをきっかけに、メイコは彼に戦い方を教えた。ヒースムーアは容赦のない地だった。この弱肉強食の世界で、彼女は弟が堂々と生きていけるだけの強さと技術を身に着けさせた。
しかし、それも遠い昔のこと。モトオリは立派な若き大蛇に、メイコは誇り高き剣聖に成長した。だというのに、またこうして、怯えた子供のように走っている。ただ弟を守ることだけを考えていた。扉ははるか先にある。もう間に合わない。モトオリが教えてくれたように、立ちあがり、戦うしかないのだ。メイコが合図をすると、モトオリはすぐに彼女の肩を叩く。幼いころに身に着けた、姉弟の声なき合図である。メイコが走る姿勢からおもむろに振り向き、モトオリが彼女の横を通り抜けた刹那、姉弟は一挙に獲物を抜いた。
しかし、二人に迫るものをはっきりと知っていながら、メイコはその姿を見て、尋常ならざる恐怖を覚えた。その二人は侍の鎧を着ていたが、人間らしさを感じさせるものはそれ以外にない。皮膚は変色し、顔は原型が分からぬほど歪み、目は妖しく輝いている。そして、耳をつんざくような咆哮。その咆哮は、歴史において最も勇敢な戦士でさえも恐怖で体をすくませるだろう。
憑りつかれた二人の侍はこちらに近付いてきた。彼らが一歩踏み出すたび、からからと骨の鳴る音が響く。一人は刀の切っ先を地面に引きずり、まるで刀が重すぎて持てないかのようだ。しかし、憑依された侍は軽々と刀を振りかざし、メイコへと切りかかるが、彼女はその攻撃を淀みなく防いだ。
妖魔は彼女の顔に向かって吠えた。その歪んだ、おぞましい声は、遠くで眠っている子供たちを目覚めさせた。メイコはその妖魔の腕を切り落としたが、それは怯むことも、下がることもなかった。噛みつこうと牙を鳴らし、切り裂かんと鋭い爪を振るっている。だが、その喉から聞こえてくる不気味な音は何なのだろうか。あれは笑っているのだろうか?
その傍らで、敵と格闘するモトオリが見えた。彼もまた、絶望的な戦いをしているようだった。二人が幼い頃、妖魔の話を聞かされたものだった。それはあの世から来たりし悪霊であり、物と人間の両方に宿ることができるのだと。はるか昔、それは彼らの祖先により退治され、霊石によって洞窟の中に封印されたのだと。子供たちは、丑三つ時になると村外れの森に行き、石の封印に触れる度胸試しをしたものだった。幼いメイコはそれに挑んだが、モトオリはしなかった。それができるほど、彼の体と心は育っていなかったのである。だが、それは子供だましの物語に過ぎなかった。毛布にくるまっている間に聞かされる寝物語だ。妖魔など誰も信じていなかった。今この瞬間までは。
それは確かにここにいる。目覚めたのだ。貪欲な不死の者たちが。
「あの短剣が要る!」弟が叫んだ。その言葉は正しかった。二人が今持っている刀では、妖魔は止められない。「魔物の短剣」が必要だった。もう一つの物語に語られる短剣。その伝説が確かなら、目の前の怪物を殺すことのできる一振り。
戦いの混乱の中で、メイコは押し返され、投げ出され、弟と引き離されてしまった。モトオリが妖魔と戦う声はまだ聞こえるが、彼女は目の前の敵の苛烈な攻撃を避けることで精一杯だった。そのとき、妖魔の動きがぴたりと止まった。まるで地獄から生まれた孤独な案山子(かかし)のように、妖魔はただ立っていた。不吉な静寂が、メイコと村全体を包む中、彼女はただ呼吸を整えることしかできなかった。刹那、ぐしゃりと何かを押し潰すような音に、メイコの身がすくむ。それは背後から聞こえたのか? それとも上から? 彼女は振り返ったが、そこには何もなかった。また正面を向くと、片腕の妖魔は消えていた。暗闇の中に退いたようだ。一瞬、メイコは戸惑った。恐怖の源はなんだったのか。突然の静寂は、自分の名を呼ぶ弟の声で破られた。メイコの心臓が胸から飛び出さんばかりに弾ける。
「モトオリ!」彼女は叫んだ。
メイコは弟のもとへ駆け戻った。姉弟がたどり着けなかった扉を最後に見た場所へと。しかし、そこには妖魔も、モトオリもいない。弟の兜だけがそこに残されていた。その兜を覆っているのは… クモの巣だろうか? もしや… また別のおとぎ話の存在が本当に現れたというのか? 最悪の事態だ。もしそれが本当なら、メイコにほとんど時間は残されていない。
弟は消えてしまった。メイコはモトオリを見つけるだろう。たとえそれで命を落とすこととなろうとも。
だが、そのためには武器が要る。あの短剣が。

パート2
古い家が、まるでその敷居をまたいでみろと言わんばかりに、丘の上から彼女を見つめていた。メイコは、微動だにしない背の高い草に挟まれた獣道を注意深く歩いた。風はなく、人間の使命など知る由もない遠くの虫と蛙の鳴き声だけが、この瞬間の黒い恐怖を満たしていた。メイコは縁側に続く古びた木の階段を上った。そして、刀を抜き、戸の代わりになっている土茶色のぼろ布を横に押し、家の中に足を踏み入れた。
モトオリが姿を消してから二日しか経っていないが、メイコにはそれよりもずっと長く感じられた。村では妖魔がはびこり、暴れまわっている。人々はどうしようもない恐怖に襲われていた。ほとんどの村人は家の中に閉じこもってしまった。そして、外に出た者は姿を消すか、恐ろしい生霊の宿主と化していた。メイコは真っ先に短剣の祭壇を訪れたが、そこには何もないと知って衝撃を受けた。村の妖魔を退治しようとした他の戦士によって持ち去られていたのだ。その戦士が姿を消してからというもの、メイコはその足跡をたどり続け、ついに寂れた丘の上にある寂れた家を見つけた。
メイコが足を踏み出すたびに軋む床板は、彼女のカタツムリのような歩みを音で伝える。メイコの動きには寸分の無駄もない。月明かりに照らされた埃がちらつくたびに周囲を観察し、短剣の所在の手がかりを探った。そのとき、くつくつと笑う声が聞こえて、メイコは立ち止まった。背中を伝う冷や汗は気にならない。恐怖に屈するわけにはいかない。笑い声は、彼女の周りをぐるぐると回っているようであり、遠くから聞こえてくるかと思えば、ほんの一寸先から聞こえてくるようでもある。しかし、何も見えない。彼女は刀の柄を両手でしっかりと握りしめ、歩き始めた。ひっくり返った椅子、割れた鍋、血のついたぼろ布を横目に通り過ぎる。この家はもう長いこと空家だった。しかし今、この家には何かが住んでいる。そしてそれは、ただひたすらに客をもてなそうとしていた。
笑い声は聞こえなくなった。しかし、その静けさに慣れる間もなく、今度は赤ん坊の泣き声が聞こえてきた。耳に全神経を集中し、メイコはその声を追って隣の部屋へと進んだ。その部屋は、かつて温もりと笑いに満ちていた台所であっただろう場所だった。しかし、その部屋の真ん中には、食卓ではなく、木のゆりかごが置かれていた。次第に大きくなり、不安をかきたてる泣き声は、そこから聞こえてくるようだった。その瞬間、メイコは気付いた。それは、生まれたばかりの弟が眠っていたゆりかごと瓜二つだったのだ。
「モトオリ」と小さく言葉をこぼし、ゆりかごに近づく。しかし、それは毛布で覆われ、中に何があるのかはわからない。耳をつんざくような泣き声を止めようと、メイコは毛布を引きはがしたが、その中にはなにもなかった… 手に絡みついたクモの巣を除いては。恐怖に襲われたメイコは慌てて糸を取り払い、立ち去ろうと振り返ると、その前には真っ白な目をした怪物の顔があった。怪物は、メイコに向かって咆哮する。悲鳴を上げた彼女はよろめき、ゆりかごにつまずき、床に倒れこんだ。
メイコを脅かした妖魔は、その目の前で形を成し、体を支える細長い脚と、生気のない細長い両腕を形作った。「弟を救うことはできぬ」その実体は、空虚で、かすれた声で言った。「あれに捕まったのならば」それは一歩前に踏み出した。「すぐにすべてが終わるだろう」もう一歩「かわいそうな弟よ」そしてもう一歩「かわいそうなモトオリ」そしてもう一歩「母の言いなりよ」
妖魔から目が離せぬまま、メイコは落とした刀を両手で必死に探る。時間を稼ぐため辺りを見回すと、あるものが目に飛び込んできた。近付いてくる妖魔の背後、ひっくり返ったゆりかごの横。白い毛布の真ん中で光るもの。あれは刃物だ。魔物の短剣だ。
化け物は長い腕を彼女に振り下ろしたが、メイコは飛び退いた。宙返りして短剣に手を伸ばし、迷わずその柄を掴む。柄を固く握りしめ、しっかりと狙いを定めて、妖魔の胸に突き刺した。妖魔が苦悶の声を上げたかと思えば、その体からあふれ出た生命力が短剣へと吸い込まれた。すべてが終わると静寂が戻り、メイコは膝をついた。
刃が手の中で青く輝くと、新たな鼓動がメイコの魂に根を下ろし、腕へと流れ込んでゆく。今しがた殺したばかりの怪物が、体の内側で蠢き、解き放たれようとしているのが感じられた。その瞬間、彼女は伝説が真実であることを知った。短剣は単なる武器ではなく、殺した悪霊の牢獄だったのだ。そして、短剣を長く持てば持つほど、その悪霊に苦しめられることになる。しかし、それが何だと言うのか。それが村を解放し、弟を救うための代償であるなら、メイコは喜んでそれを払うだろう。
もはや一刻も無駄にはできない。「今行くよ、モトオリ」彼女は呟いた。「死なないで」

パート3
メイコは、自分がどこにいるのか、何をしているのか、ほとんど理解できていなかった。周囲からは彼女に命令する人々の怒鳴り声が、空を引き裂くような恐ろしい絶叫となって聞こえてくる。燃え盛る体が横を通り過ぎたかと思えば、時の流れが遅くなる。何が現実で、何が現実でないのか、まったくわからない。霧がメイコの肌を焼いた。動くたびに、一歩一歩進むたびに、激しい苦痛が襲う。悪霊たちはメイコの肌の上に姿を現し、彼女の中で互いに、そして彼女自身と、体の支配をめぐって戦っていた。
短剣を寂れた家で手に入れた後、彼女は戦場へ赴き、6体の妖魔を退治した。伝説では、魔物の短剣は妖魔を滅ぼせば滅ぼすほど力を増すと言われている。そして、それは真実だった。彼女は全身に力がみなぎるのを感じ、肉体という束縛から解き放たれようとする激しい嵐を感じた。殺すたびに、彼女はより強くなったが、同時に自分自身も失っていった。悪霊は彼女に語りかけ、悲鳴を上げ、懇願し、泣き叫び、影へと誘った。そして、時が経つにつれ、その誘惑はますます強まっていった。受け入れるのは簡単だ。彼らに屈するのも、彼らに支配されるのも。だが、彼女はできなかった。たとえそれが目の前にあったとしても。
地獄のような化け物の叫び声が、襲来を知らせた。メイコは純粋な本能によって反応し、ほんのわずかの間澄んだ頭を取り戻し、漆黒の覆いがはがれ、今ここにある悪夢に引き戻された。それはクモだった。どんな人間や動物よりも大きく、その脚は木のように太く、その爪は剣よりも鋭かった。巨大な腹部には犠牲者の顔が張り付いている。そして、その巨大な体躯の上には、女の上半身が乗っている。その顔は絹糸のような白い髪に覆われていた。ともすれば、メイコは奇妙な美しさすら覚えたかもしれない… それがこの世で最も恐ろしい存在でなければの話だが。女郎グモ。殺戮の女王。悪霊の母。
メイコは手にした短剣に意識を集中させた。手のひらに触れる冷たい柄。信じられないほど軽く、同時にありえないほど重い。響き渡る声がより鮮明になった。刻まれた紋様の一つ一つが、彼女の指にぴたりと馴染む。響く声が鮮明になっていく。それは妖魔の声ではなく、彼女の隣で戦うことを選んだ戦士たちの声だった。メイコが彼らの名前を思い出ずとも、彼らは彼女の名前を知っていた。彼らはその名を叫び続け、彼女に助けを求めていた。そのとき、メイコは自分がどこにいるのか、そして、なぜ市場の中心にいるのかを思い出した。
8本の脚で動く蜘蛛には、魅了されてもおかしくないほどの、奇妙な優雅さがあった。その非現実的な美しさは、殺戮の序章に過ぎなかった。一人の戦士がメイコの目の前で真っ二つにされた。また、ある者は吹き飛ばされ、その衝撃で全身の骨が粉々に砕け散った。ある者は猛烈な炎の玉に巻き込まれ、そのまま首を落とされた。倒れた者たちの血にまみれながら、メイコは自分が泣いていることに気づいた。しかし、その涙が自分のものなのか、それとも自分の中にいる悪霊のものなのか、彼女にはわからなかった。
想像を絶する存在を倒すという絶望的な望みのために戦士が次々とその身を犠牲にしていく中、メイコはその悪臭と熱気を感じられるほど、女郎グモに肉薄した。刃は彼女の手の中で震えている。それは彼女の意思に逆らい、彼女を進ませまいとしていた。妖魔の声が頭の中に蘇り、もはや抑えきれないほどの激流となった。「もう私に関わるな」と叫びたい気持ちが襲う。メイコはもう一度、なぜこうして戦っているのか、大切なことに心を定めようとした。モトオリ。彼女は弟の声、そして、弟の強さを想った。弟の心に思いを巡らせた。幼い頃、洞窟に近づこうとしなかったこと。「嘆きの夜」を行うことで自らを証明しようとする姿。弟への愛。それだけで十分だった。
大いなる剣聖の力を借り、渾身の力を込めて、短剣をクモの心臓に突き刺した。怪物が甲高い悲鳴を上げたかと思うと、その死骸から青い光が放たれ、刃に吸い込まれていった。悲鳴の残響が消えると、メイコは膝をつき、光は消えた。すべて終わったのだ。
彼女は地面に横たわり、体の震えを止めようとする。体中の骨が折れそうになっていた。血の流れている手に目をやると、短剣を強く握るあまり、皮膚に食い込んでいた。視界がぼやけ始めた。残された時間は少ない。するとなぜか目の前にモトオリが現れ、彼女は最後の光景が恐怖ではなく、愛する者の幻だったことに感謝した。しかし、それは幻ではないことに気がついた。モトオリは確かに生きて、そこにいたのだ。髪も服もクモの巣にまみれていた。どの仲間が彼をクモの巣から助け出したのかはわからない。しかし、そんなことはどうでもよかった。彼女はやり遂げたのだ。弟は五体満足で生きていた。約束は守られた。
目に涙をたたえながら、メイコは両の腕で弟を抱きしめた。姉弟は再び相まみえた。だが、その時間ももう長くはない。
「モトオリ」一言一言声を震わせながら、メイコは伝える。「あなたに頼みたいことがあるの」
***
弟と村を救うためにすべてを犠牲にした剣聖メイコの物語は、寺院の庭園の誰もが知っている。女郎グモを退治した後、自分が最悪の妖魔になることを恐れたメイコは、かつて悪霊の牢獄として使われていた洞窟に自らを封印するよう弟に言い残したとされている。
洞窟の石の扉に触れる度胸試しは、今なお子供たちの間で続いている。しかし、それは恐怖から行われているのでなはい。彼らは皆、斬魔の勇士と呼ばれる剣聖に敬意を表し、その勇気を受け継いでいるのだ。
おすすめコンテンツ

バトルパス&レガシーパス
失われたホルコスの財宝がついに発見された。伝説の海賊船長コールハートが財宝を我が物にしようと船出する。だが船長の思い通りには事は運ばない。ヒースムーアの偉大なる戦士たちも我先に富を求め、争いに発展する。こうして刃が宝の山の上でぶつかり合う。財宝の中には、海の戦士たちの名高き武器もまぎれている。それは幾世代にもわたり、宝を懸けた戦いが続いてきたことの証左だ。財宝は終わりなき争いの連鎖を生み、永遠の果たし合いの種となってきたのだ。
帆を掲げ、栄光の戦利品を略奪せよ。Y9S2バトルパスではヒーロー全員に向けた100ティアのリワードが解除可能!
最新のレガシーパスも忘れずにチェックしよう。Y5S2から復刻したリワードが手に入るほか、101ティア到達の新たな限定リワードも入手できる。
「フォーオナーY9S2: 反抗」の期間中のみ利用可能。
詳しく見る
新しいカトゥーンキャラクター
ハトゥンは、2本の剣を操る残忍かつ機敏な暗殺者集団だ。彼らはグルジンの率いるモンゴルの大軍勢と共にヒースムーアへ侵攻する。その目的は、グルジンが思い描く理想である、長きにわたり民たちを蝕んできた些末な戦乱から解放された平和なヒースムーアの実現。たとえ如何なる代償を払おうとも、グルジンの帝国の元に統一された平和なヒースムーアを作り上げるのだ。