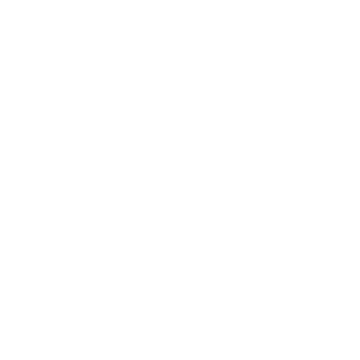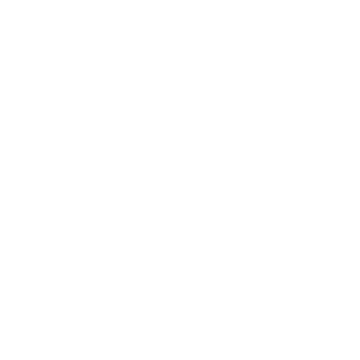無名のナイト ヒーロースキン

無名のナイトは、その名の通り、真の名を誰も知らぬ英雄である。幼いころはどこにでもいる泥棒で、生きるために盗みを働いたり、物をあさったりしていたという。だがあるとき、彼女が盗みの標的にした貴族の騎士は、その娘の内に光るものを見た。騎士は娘を追い払うのではなく、自分の下に置き、ウォーデンとして彼女を鍛えた。何年もの時を経て、今はなき騎士団の技と精神が、彼女に受け継がれた。こうして彼女の心には、助けの手を差し伸べるという信念が深く根付くことになったのである。
騎士は死の間際、従者に自らの剣「ヴァローズエッジ」を託した。長年にわたり騎士は、この剣が騎士の歴史においてどのように扱われてきたか、そして、この剣が今なお重要なものであるか、その全てを従者に伝えてきた。騎士は従者に自らの剣を託し、騎士たちの遺産を受け継ぎ、大変動の後の世界に残された人々を助けよと命じた。そしていつの日か、この剣の誓いは果たされ、騎士団はひとつの旗の下に団結するだろう。
ヒースムーア世界の物語

パート1
その日は、いつもと変わらない薄暗い日だった。太陽が雲の間から顔をのぞかせたかと思えば、闇が辺りを包んだ。いつものように、娘は夜明けに目を覚ました。それは訓練の一部であった。「知者は誰よりも早く身を起こす」始めの頃、師である騎士がよく言っていたことだ。彼はいつもこのような言葉を口にし、彼女はその全てを記憶した。それは態度を学ぶための訓練であり、騎士が娘を自分の下に置いてから最初に教えたことのひとつだった。
今となっては、それははるか昔のことのように思えた。幼き頃の彼女は、生きるために盗みを働いていた。彼女は騎士に忍び寄り、彼のわずかな財産を盗み取ろうとした。ところが娘は騎士に捕らえられてしまう。剣を一振りすれば、それで全てが片付いただろう。しかし、その日、灰色の雲から太陽の光が差し込む数少ない瞬間に、騎士は別の選択をした。あの日の騎士が自分の中に何を見たのか、何度も考えている。今、彼女は従者となっていた。ウォーデンとなるため、騎士道の何たるかを学んでいる。ときおり、自分が偽物のような気持ちになる。この人生は他の誰かのものではないかと。盗人よりもずっと価値のある誰かの。
絶え間ない風に背中を押されながら、乾いた土を踏みしめる。彼女は剣の柄をしっかりと握りしめた。まるで、その行為だけが自分を支えるかのように。鋭くそびえ立つ岩山を乗り越え、なんとか身が通るほどの洞窟を通り抜け、干上がった渓谷を探索する。彼女はまたしても、指示された場所の先を越えて探索を進める。毎日、少しでも遠くを目指し、歩き続ける。水を、食料を、そして、助けを求める生存者たち探し求めて。「民を第一に考えよ」もっとも重要な教えだ。幸運に恵まれる日があれば、そうでない日もあった。半日経ったが、今のところ生存者には出会っていない。見つけたのは、枯れかけた木から集めた一握りの乾いた木苺だけだった。全員に行き渡るほどではないが、それでどうにかするしかなかった。

パート2
その帰り道、遠くから争いの音が聞こえてきた。それが自分の野営地、つまり、彼女と老人と3人の生存者が家と呼ぶようになった小さな廃墟の一角から聞こえてくるのだと気づいたとき、彼女の心は不安でかき乱された。鎧が重くのしかかるなか、彼女は歩を早めた。胸のうちの鼓動に気付かないふりをしながら、恐怖を脇に押しやり、呼吸するよう体に命じた。
襲撃者を目にしたそのとき、彼女はすでに剣を抜いていた。盗賊だ。数は5人、剣で武装していたが、彼らを師が食い止めていた。師の背後には3人の避難民が身を寄せ合っていた。みな恐怖に縮こまり、震えている。
戦いに駆けつけるや否や、彼女は騎士の背中へと振るわれた剣を受け止め、その相手を弾き飛ばした。
「“いかなる時も後ろを取られるな”という教えを思い出しますよ」彼女は騎士に言った。師をからかったのだ。
「こちらに来るお前が見えたからな」荒い呼吸を隠そうともせず、老いた戦士は答えた。
「そうでしょうね」そう言いながら、彼女は2人の敵からの攻撃を受け流した。相手は死に物狂いだった。腹を空かせている。飢えているのだ。どんな代償を払ってでも生き延びることしか考えていない。彼女は、師が傷を負っていることを察した。全盛期の戦いぶりは見事なものだった。しかし、今はもう老いてしまい、盗賊に奇襲を許してしまったのだろう。
強盗のひとりが彼女に襲いかかったが、彼女は体を捻ってその攻撃をかわし、その勢いを利用して相手の背中を切り裂いた。顔を上げると、騎士がもうひとりを切り伏せている瞬間が目に入った。その手に握られているのは伝説の剣、ヴァローズエッジだ。その剣にまつわる逸話は、騎士からいくつも聞かされた。そして、その剣がある理由と重要性についても、この剣を受け継いできた代々の使い手たちのことも。その全員が英雄であり、真実の導き手であり、美徳の模範だった。夜、彼女は彼らの物語、武勲と偉業を夢に見た。心の奥深くで、自分がその中に加わるに相応しいか否かを考えた。
背後にいた騎士が、痛みにうめいた。さらに一太刀を受け、足元にはおびただしい血がまき散っていた。騎士は切られた勢いのまま倒れ、彼女はその相手に体全体でぶつかり、彼を守った。そして、もうひとりの胸に剣を突き刺し、振り向きざまに倒れた盗賊へ剣を振り下ろした。彼女が体勢を立て直そうとした瞬間、最後の盗賊が怒号を上げながら、剣を頭上に掲げて彼女に猛然と襲いかかった。剣が振り下ろされようかという刹那、彼女は武器を振り上げて攻撃を防いだ。しかし、敵の剣はその弱々しい刃を折ってしまった。
盗賊の剣は彼女を皮一枚はずして地面に突き刺さった。盗賊は最後の一撃を加えようと、次の攻撃に備えた。束の間、すべてが失われたように思えた。終わりだ。師の命は風前の灯火だ。彼女も、そして避難民たちも殺されるだろう。やはり、そうだったのだ。自分は騎士ではない。自分には資格がなかったのだ。
「違う」彼女はその考えをはねのけた。かつて、師は自分の中に何かを見た。そして、何かをすれば——それが何であろうと——師の正しさを証明できるのだ。
従者は好機を無駄にしなかった。折れた剣の柄を手にしたまま、彼女は折れた剣先を盗賊の首に突き刺した。その顔に複雑な混乱の色を浮かべながら、男は仰向けに倒れ、暗赤色の血が肉を押しのけて噴き出した。粉々に砕けた一寸の金属が、盗賊の人生、そして、戦いに終止符を打った。

パート3
兜を脱ぎながら、従者は師のそばへ駆け寄った。彼の呼吸は絶え絶えで、その口元から血がしたたり落ちた。彼女はひざまずき、師の手を取った。両目からあふれ出る涙には抗うことができなかった。
「ありがとう」師の声は小さかった。
「なぜ礼を言うのですか?」彼女は問うた。
「この老いぼれにもう一度… 希望を… 見せてくれたからだ…」
目から光が消えつつある騎士は、拳を胸に当てた。その指はヴァローズエッジの柄を握ったままだった。そして、指の力がゆるみ、手を離した。
「剣を取れ」騎士は命じた。「お前が継ぐのだ…」
彼女が師の顔を抱きしめると、涙が頬を伝った。今起きていることを、理解できずにいた。「いかないで」彼女は乞うた。
「もう私がおらずともよい」か細い声を漏らした口は、かすかにほほ笑んでいた。「大丈夫だ」
そして、騎士はこと切れた。震える手で、彼女は彼の瞼を下ろした。わずかな間——ほんの数瞬の間——彼女は息を整え、悲しみに暮れることを自分に許した。次の瞬間には、もう手は震えていなかった。ヴァローズエッジの柄を握り、編み込んだ髪を風になびかせながら立ち上がった。
彼女は近くにいた避難民の方を向いた。少年だ。自分が師と出会ったときの年頃とそう変わらない。彼女はもう片方の手をそっと差し伸べた。
その手の上には、集めてきたわずかな木苺があった。
民を第一に考えよ。
おすすめコンテンツ

バトルパス&レガシーパス
失われたホルコスの財宝がついに発見された。伝説の海賊船長コールハートが財宝を我が物にしようと船出する。だが船長の思い通りには事は運ばない。ヒースムーアの偉大なる戦士たちも我先に富を求め、争いに発展する。こうして刃が宝の山の上でぶつかり合う。財宝の中には、海の戦士たちの名高き武器もまぎれている。それは幾世代にもわたり、宝を懸けた戦いが続いてきたことの証左だ。財宝は終わりなき争いの連鎖を生み、永遠の果たし合いの種となってきたのだ。
帆を掲げ、栄光の戦利品を略奪せよ。Y9S2バトルパスではヒーロー全員に向けた100ティアのリワードが解除可能!
最新のレガシーパスも忘れずにチェックしよう。Y5S2から復刻したリワードが手に入るほか、101ティア到達の新たな限定リワードも入手できる。
「フォーオナーY9S2: 反抗」の期間中のみ利用可能。
詳しく見る
新しいカトゥーンキャラクター
ハトゥンは、2本の剣を操る残忍かつ機敏な暗殺者集団だ。彼らはグルジンの率いるモンゴルの大軍勢と共にヒースムーアへ侵攻する。その目的は、グルジンが思い描く理想である、長きにわたり民たちを蝕んできた些末な戦乱から解放された平和なヒースムーアの実現。たとえ如何なる代償を払おうとも、グルジンの帝国の元に統一された平和なヒースムーアを作り上げるのだ。