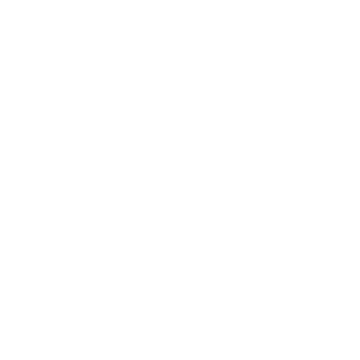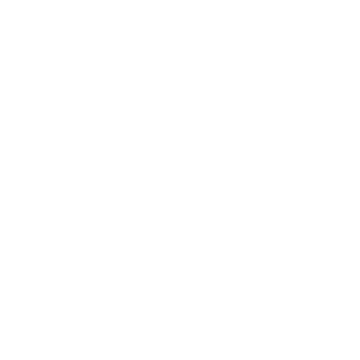ブラックプライア用スキン「指揮官レイヴィア」

イグニス山が噴火したとき、炎と溶岩が山道をすべて焼き尽くした。その日、レイヴィアは火傷を負い、すぐに仮面でそれを隠した。ある者は、彼女がひどく醜い姿になったと言い、またある者は、彼女の受けた傷は小さく、その日本当に傷ついたのは彼女の自尊心だけだったと言う。しかし、真実ははるかに恐ろしいものだ。レイヴィアが仮面をつけたのは、自身を隠すためではなく、本当の自分、「死の化身」をさらけ出すためだったのである。それは不変で、読めず、止められない存在だ。 無慈悲な性格ととりわけ残酷な行為によって、レイヴィアはヴォーティガンの目に留まり昇進した。指揮官レイヴィアルは、ヴォーティガンの右腕としてブラックプライアを多くの勝利に導いた。肉体を失った犠牲者や恐怖の逸話を残した彼女は、いつしか「レディ・ミザリー」という名で知られるようになった。
アラビアに眠る強力な秘宝の噂を耳にしたヴォーティガンは、指揮官ラヴエを遠方の王国へと送りこんだ。その地はかつて行き着くことができなかったが、新たな道が開拓されたおかげでとうとう手が届くようになったのだ。レイヴィアは使者に成りすまして国王妃と会い、君主の夢や願望を難なく読み取った。欺瞞によって国王妃の支持を得たレイヴィアは、未来を予言することができる遺物「天球」を使えるようになった。ヒースムーアに待ち受ける未来を知ったレイヴィアは、遺物を破壊し、国王妃を殺害した。そうすることで、自分だけが未来の秘密を握れるようにしたのだ。それから起こることは彼女だけが知っていた。その名は「悲惨(ミザリー)」だった。
悲惨の力

パート1
夕暮れに星がかすかに輝いていた。刻々と消えゆく残り少ない陽光によって、空は桃色に照らされ、ますます暗くなり、そして赤く染まっていった。しかし、月はどこにも見あたらなかった。おそらく、月は殺戮が繰り広げられていることを知っていて、少しでもそれを見たくないという思いがあったのだろう。
戦いが起こっていたのは、鋭利な岩や昔は希望に満ちた花を咲かせていた枯れ木が散乱する黒土の原野だった。熱を帯びた霧が低く立ち込み、強風に支配された渦が絶え間なく巻き起こる。それはまるで、敵であるキメラの同盟をほとんどやみくもに攻撃した黒衣の騎士たちに歯向かっているかのようだった。刃が硬い盾に当たると隊列の間隔が狭まり、攻撃を食い止めるための強固な結束が形成されていく。彼らは数で負けていたが、後退することはなかった。彼らはブラックプライア、誇りがその原動力だ。命乞いはしない。決して降伏はしない。彼らは最後まで戦うのだ。
夜の闇が落ちた頃、ブラックプライアは高すぎて登ることのできない岩壁まで押し戻されていた。絶体絶命だった。しかし、キメラの兵士たちが最後の攻撃をしようと移動したその瞬間、何かが起きた。大きな叫び声が夜に響き、彼らは皆後ろを振り向いた。その音は馬から発せられたものだ。松明を手にした騎手を乗せ、馬が突進してきた。炎は霧によって弱まった。その輝きは騎手の光沢のある面頬に反射し、頭に被った茨の冠と、黒く澄み切ったのぞき穴を際立たせていた。
キメラ兵の何人かは怯えた様子だった。恐怖で隊列を崩す者も現れ、足をもつれさせる者さえいた。その騎手は有名だった。彼らは誰がやって来るのかわかっていたようだ。それは指揮官レイヴィア、ヴォーティガンの右腕だ。しかし、戦場に立つ者にとって、彼女は別の名である「レディ・ミザリー」と呼ばれていた。
敵陣に到達する前に、レイヴィアは大きな袋を投げつけた。その袋は空中で回転しながら周囲に液体をこぼし、何人かのキメラの戦士に液体をふりかけた。そのうちの1人は、不運にも袋を取ってしまい、手にしたとき、初めてその液体の正体が油であることに気づいた。だが、すでに手遅れだった。レイヴィアがすでに松明を投げいたのだ。突然、炎が初夜を照らし、辺りに悲鳴が響き渡った。燃える兵士たちはなすすべもなく走り回り、互いに衝突し、火をさらに広げていった。指揮官は剣を抜き、盾を片手に馬から飛び降りた。追い詰められていたブラックプライアも再び戦いに加わり、最も近くにいるキメラの戦士に奇襲を仕掛けた。
その後、戦いが長く続くことはなかった。
レイヴィアは立ち向かってくる者をすべて殺した。炎に包まれている者もそうでない者も、走って叫んでいる者も。そして残りの者たちは彼女の仲間が相手をした。程なくして、レディ・ミザリーとブラックプライアは、多数の屍の中に立っていた。周囲には小さな火が燃え、黒い鎧を照らしていた。それはまるで冥界の深淵を占領したかのようだった。彼らはあと一歩で敗れるところだったが、幸いにも指揮官が間一髪で間に合った。この数年、彼女はイライラを募らせていた。戦いの数は多くても、勝利の数はあまりにも少なかったからだ。この戦いの流れを変えたように、彼女が戦争の流れを簡単に変えることがないものだろうか。
彼女は「ヴォーティガンから招集された」とだけ彼らに伝えた。ブラックプライアが正統な指導者に謁見することは稀であった。今日では彼の姿を見ることさえほとんどなかった。それはつまり、彼が話す内容が最も重要であるということだ。レイヴィアだけが天幕に入った。他の者たちは外に立って馬のそばで待機し、夜に向かって伸びる高い崖を見上げていた。
彼女は天幕に長く留まらなかった。外に出てきた彼女の金属製の顔からは、相変わらず何を考えてるのか読めなかった。彼女は馬の上に乗り、仲間たちに必要なことをすべて話した。
「東へ進む」
「目的地は?」とブラックプライアの一人が尋ねた。
「アラビアという土地だ」と彼女は言った。冷たく無表情な仮面の下で、彼女は微笑んだ。

パート2
大書庫に立ち入るのは簡単ではなかった。砂漠を横断する長旅の末、指揮官レイヴィアと彼女が最も信を置く数人のブラックプライアは、アラビア王国の荘厳な門にたどり着いた。漠然とした思いで東へと旅したレイヴィアだったが、このように戦いとは無縁に見える、繁栄する国と出会うとは予想もしていなかった。国を治める国王妃は、他の誇り高き指導者たちと同じように泰然としていた。しかし、レイヴィアは彼女に違和感を覚えた。その微笑みに偽りはなく、暖かさを醸し出していた。まるで善人のように見えたのだ。それはレイヴィアを限りなく苛立たせたが、同時に彼女が標的を意のままに操れるということでもあった。ここはレディ・ミザリーではなく、レイヴィアの出番なのだ。そうして彼女は、宴を仕事の場とした。友情、富、そして強力な同盟関係を約束し、国王妃を説き伏せ、アラビアで最も貴重な遺物を使ってもよいと許しを得た。国王妃の側近たちは、あらゆる手を尽くして彼女に思いとどまるよう説得した。しかし、レイヴィアは国王妃に爪を立て、彼女のうぬぼれを食い物にしたのである。
もう夜更けに差し掛かるころだったが、レイヴィアは今すぐ書庫に向かうべきだと言った。この忌まわしい王国で過ごす時間を少しでも短くしたかったからだ。この国に満ちる鼻を突くような平和と充足の臭いに、レイヴィアはほとほと嫌気が差していた。松明を手に、彼女は螺旋階段を上り、部下たちがそれに続いた。彼女たちは書庫の中を自由に歩くことが許されていたが、レイヴィアは自分たちが厳重に見張られていることに気付いていた。国王妃は彼女を信頼していたかもしれないが、書庫の漆黒の影に潜む数多くの目に、信用されていないのは明白だった。こうでなくては。レイヴィエはそう思った。この場所でも、やはり戦いがあるということだ。
ようやく書庫にたどり着いたレイヴィアは、その中身に感心せずにはいられなかった。白い大理石の壁が、横にも縦にも、計り知れないほど遠くまで伸びている。その壁はすべて巨大な書架で覆われ、色とりどりの革装本、糸で巻かれた羊皮紙の束、乱雑に積まれた写本で埋め尽くされていた。メインホールにはさらに数十の書架が円を描くように並んでいて、どの棚にも少しの隙間もなく書物が収められている。上を見ると、天井には精密な星座と思しきものが描かれ、その中央にある丸い小穴からは月と星々の光が降り注いでいる。そして、その光が真っ直ぐと下りた先にあるものこそが、大書庫の心臓でありレイヴィアの長き旅の目的である天球だった。これこそが、ヴォーティガンが切望する遺物だ。
球状のアストロラーベは小さな台座の上に乗せられており、その周囲には歯車のような金の細い輪が浮かんでいる。それに近づくと、奇妙な囁きが重なって聞こえる。その意味を理解できるとも理解できないともつかない、遠くからの声だ。遺物に近づけば近づくほど、その声は大きくなっていった。それはほとんど歌のようで、運命の呼び声のようだった。神への賛美歌のようにも思える。レイヴィアは金の輪の間から手を伸ばし、ガラスの球体に触れた。すると、言葉にできる理由も理屈もなく、指先が吸い寄せられ、彼女は直感的に何をすべきかを理解した。球体の封印が解かれ、その中に太陽の中心のような眩い光が見えた。
一瞬のうちに、レイヴィアの目の前に景色の波が押し寄せた。すでに知っている出来事が次々と映し出される。これまでに起きたこと、つまりは過去の一つ一つが現在のビジョンに流れ込んできた。そして、まだ見ぬ世界が広がっていく。ヒースムーアの未来。離れてはいても、手の届くところにある。数え切れないほどの痛み。そして苦悩。彼女が望んだ以上に、すべてはそこにあった。覇権への羅針盤。そしてそれは彼女の手にあった
光が落ち着きを取り戻すと、汗が仮面の奥からしたたり落ちた。うつむいたままレイヴィアは息を整え、球体から突然与えられた知識の意味を理解した。もしそれを余さず利用できれば、他の誰も彼女が何をしたかを知ることはできない。しかし、それに伴う危険はあまりにも大きい。一瞬、すべてが静寂に包まれた。だが次の瞬間、レイヴィアの手にはすでに剣が握られていた。彼女は遺物に剣を振り下ろし、黄金の輪もろとも粉々に砕いた。叫び声と、こちらに押し寄せる足音が聞こえてくる。
部下のブラックプライアたちはレイヴィアを囲んで隊列を組み、戦闘態勢に入った。
「燃やせ。一つ残らずだ」彼女はそう命じた。

パート3
レイヴィアの心にもう曇りはなかった。自分がこれから向かう先も、しなければならないことも分かっている。彼女の行動によって、状況はすでに動き出した。大書庫の破壊は予見されていなかったとしか考えられなかった。もはや彼女の知っていることが他の誰にも知られる心配はない。その知識はあまりに貴重で、他人に託すにはあまりに危険すぎた。運命は気まぐれで、ほんの小さな花びらが散るだけでその流れが変わってしまう。レイヴィアに花を愛でる心はない。しかし、価値のない者たちの血に濡れた大地に咲いている花であれば、彼女はそれを確かに育むだろう。
彼女とその部下は、ほとんど休むことなく急ぎヒースムーアに戻った。砂漠の王国からの脱出で命を落としたブラックプライアが2人だけだったのは、まさに幸運だった。背後に見える煙の柱は、王国を離れて数日が経っても消えることはなかった。それは彼女たちの力を証明するものであり、ホルコスの力がヒースムーアの先まで及んだことを世に知らせるものだった。王国から離れるほど煙は薄くなり、やがて視界から消えていった。
砂漠はいよいよまばらになり、草原、緑の森、流れる川が現れた。そして平原に岩場が増え、やがて地平線上に広がり、前方の空には山々が並んだ。見慣れた景色。彼女たちは故郷に戻ったのだ。レイヴィアは決して口に出しては認めなかったが、あえて言葉にするなら、「帰ってこれてよかった」と言っただろう。砂漠は空虚で、生命も、紛争すらもない白紙の地だった。この緑豊かなヒースムーアで、彼女はすでに冷たい死の予感を感じていた。何もかも正しく感じられた。
渓谷の端にさしかかったとき、レイヴィアは足を止めた。周囲を観察してから、雲一つない空に目を留める。真昼を過ぎたばかりの太陽がまばゆく輝いている。その光は強く暖かかったはずだが、彼女の肌には一筋も触れていない。レイヴィアは鎧の暗闇を好んだ。それは今までも変わらない。彼女がさりげなく刀の柄に手を回し、軽く柄頭をなでたとき、ブラックプライアたちはそれが戦いの合図だと知る。そして、レイヴィアが踵で馬の脇腹を軽く叩くと、全員は示し合わせたように速歩で前方に駆けた。
最初のメジャイが飛びかかってきたとき、レイヴィアの剣はすでに高く掲げられていた。空中でその男を捕らえ、胸を突き刺した。地面に倒れたとき、すでに彼は絶命していた。その後、他の者たちが渓谷の両側から飛び降りてきた。キメラの印を持つ戦士たちによる待ち伏せだった。レディ・ミザリーの手で焼かれた者たちの仇を討つため、彼女を始末せよと命じられたのだ。しかし、レイヴィアは不意を突かれたのではなく、むしろその逆だった。彼女はこの奇襲を予見しており、その知識を利用したのだ。天球が示したビジョンが本物であると確かめ、運命を自分の望む道に変えられるという確信を得るための試練として。
戦いは長くは続かなかった。攻撃を予知されたキメラの戦士たちは奇襲の利を失い、ブラックプライアは一気呵成に攻撃を仕掛けてきた。四肢が切り飛ばされ、深紅の血が渓谷の白い地面一面にこぼれた。レイヴィアは、敵が易々と弄ばれる様を喜びと共に眺めた。あの月のない夜、敗北を目の前にしたブラックプライアたちを寸前で助け出したレイヴィアにとって、発揮された天球の力はあまりに魅力的だった。これは勝利をもたらす力だ。ヴォーティガンは喜ぶだろう。それはもはや疑いようもない。彼女は見たことをすべて彼に伝え、次に何をするべきか説明するだろう。すべての始まりは、あの遺物の数々にある。だが、それは未来の話だ。
戦場でレイヴィアは、敵の指揮を執っていたウォーデンを探し当てた。他愛もない相手だった。決着はすぐについたが、彼女はそのウォーデンを殺さないと言った。彼の鎧を剥ぎ取り、斜めに傾いた平らな岩に縛り付け、灼熱の太陽の光にさらす。素肌がじりじりと焼けていき、ウォーデンは縄を解いてくれと乞い叫んだ。
レイヴィアは、その男が生きるか死ぬかも分からぬまま置き去りにした。結局のところ、天球が示したのは道筋だけだったということだ。だが、謎が残されているというのなら、それも一興だろう。
おすすめコンテンツ

バトルパス&レガシーパス
失われたホルコスの財宝がついに発見された。伝説の海賊船長コールハートが財宝を我が物にしようと船出する。だが船長の思い通りには事は運ばない。ヒースムーアの偉大なる戦士たちも我先に富を求め、争いに発展する。こうして刃が宝の山の上でぶつかり合う。財宝の中には、海の戦士たちの名高き武器もまぎれている。それは幾世代にもわたり、宝を懸けた戦いが続いてきたことの証左だ。財宝は終わりなき争いの連鎖を生み、永遠の果たし合いの種となってきたのだ。
帆を掲げ、栄光の戦利品を略奪せよ。Y9S2バトルパスではヒーロー全員に向けた100ティアのリワードが解除可能!
最新のレガシーパスも忘れずにチェックしよう。Y5S2から復刻したリワードが手に入るほか、101ティア到達の新たな限定リワードも入手できる。
「フォーオナーY9S2: 反抗」の期間中のみ利用可能。
詳しく見る
新しいカトゥーンキャラクター
ハトゥンは、2本の剣を操る残忍かつ機敏な暗殺者集団だ。彼らはグルジンの率いるモンゴルの大軍勢と共にヒースムーアへ侵攻する。その目的は、グルジンが思い描く理想である、長きにわたり民たちを蝕んできた些末な戦乱から解放された平和なヒースムーアの実現。たとえ如何なる代償を払おうとも、グルジンの帝国の元に統一された平和なヒースムーアを作り上げるのだ。